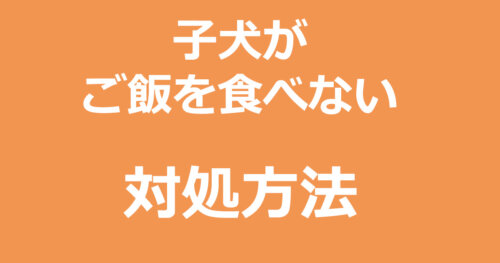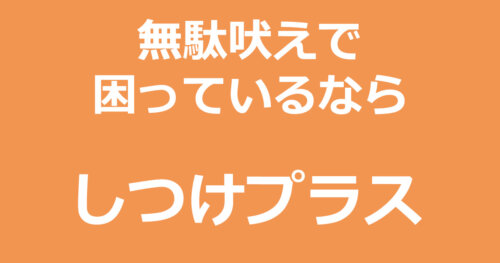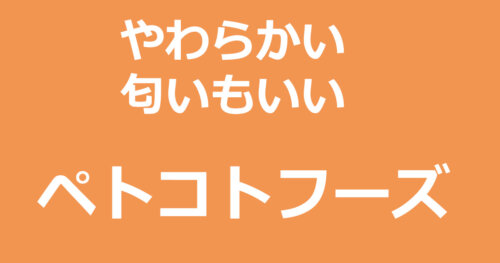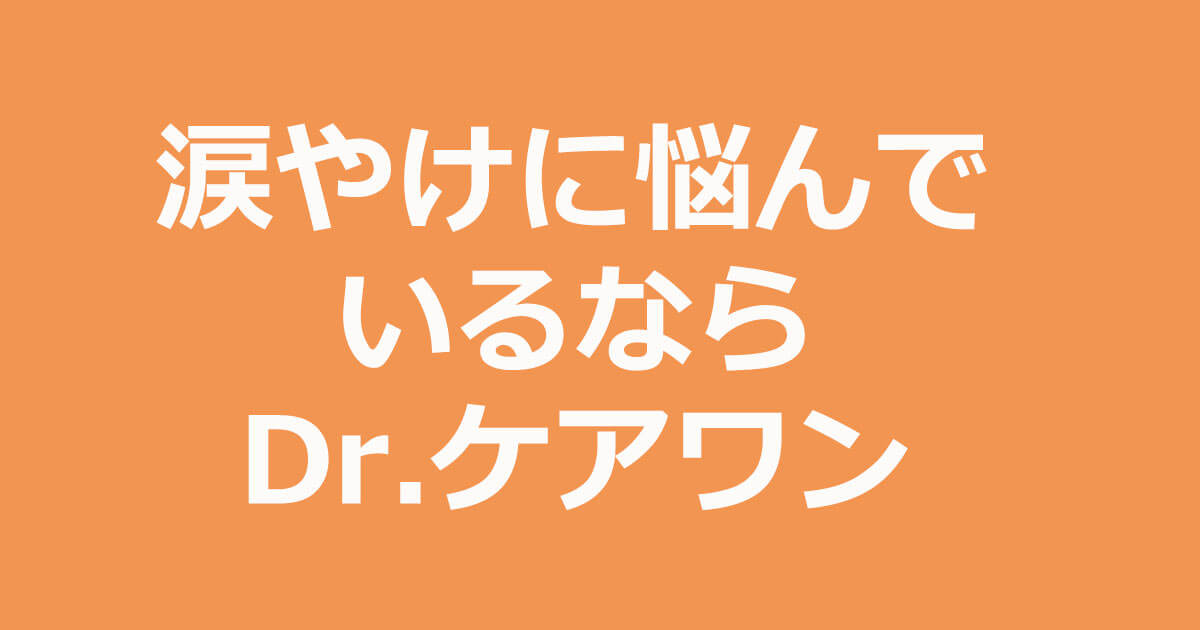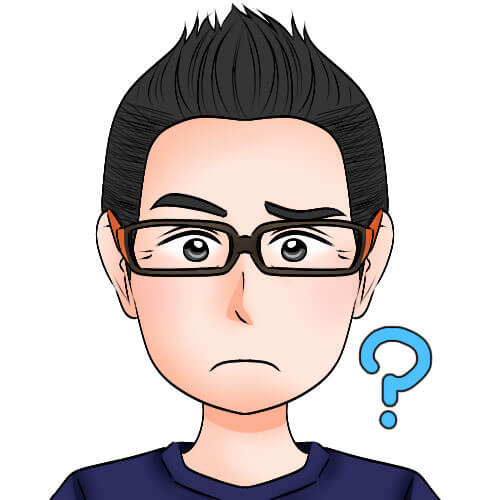
犬の「待て」のしつけがうまくできません。
どうしたら犬に「待て」をしつけることができるでしょうか。
こんなお悩みにお答えします。
- 「待て」のしつけをする理由
- 待てのしつけの環境作り
- 「待て」のしつけをする
- 待てをどこでもできるようにする
- 待てができないときは
今回は犬の待てのしつけについてお話しします。
犬の待ては、ご飯の前で待たせることだけでなく、危険あら身を守ったり、飼い主がストレスなく生活するための大切なしつけです。
そこで本記事では、犬の待てがどこでもできるように、大切なポイントだけをわかりやすく解説していきます。
「犬の待てをしつける理由は?」「犬がいうことをきかない」といった疑問も解消できますよ。

それでは、早速はじめていきましょう。
犬に「待て」のしつけをする

待てをすると、といいことがある
犬が待てをしたら、おやつを与えて、褒めてあげましょう。
おやつをもらえたり、褒めてもらえれば、率先してやってくれるはずです。
おやつがもらえるから、待てをする、褒めてもらえるから待てをするでいいのです。
2秒待てをさせる

犬の待ては、短い時間からしつけていきましょう。
おしわりの状態から待てと声をかけて、待てをさせます。
1、2秒でも待てたら、おやつを与えて褒めてあげます。
2秒の待てのやり方
- おすわりをさせます
- 「待て」と声をかけます。
- 2秒たったらおやつのごほうびを与えます。
- ごほうびを与えるのと同時に、高い声で「いいこ、いいこ」などとほめてあげたり、体を撫でてあげます。
犬にとって、2秒間、待てができたことは、成功体験です。
成功したら、ほめてあげて、2秒間確実に「待て」ができるようにしつけていきましょう。
10秒待てをさせる
犬の「待て」が2秒間、確実にできるようになったら、今度は10秒間に挑戦してみましょう。
そこで大事なのは、犬との信頼関係です。
犬が「待て」をするのは、10秒待った後に、ごほうびがもらえるからです。
おやつは犬の見えるようにして、アイコンタクトをしっかりして、10秒間待たせましょう。
犬が「待て」ことができたら、奇跡が起きた!ぐらいの感じで、喜びあいましょう。
あわせて読みたい
-

-
アイコンタクトは子犬のしつけの基本。教え方は?
2024/4/4
こんなお悩みにお答えします。 今回は子犬を飼う人ののために、大切なアイコンタクトのしつけ方法をご紹介します。 子犬をしつけをしようと思ったときは、とにかく目を合わせて、指示を出すことがとても大切です。 ...
OKで解放してあげる
犬に、待てをさせたあと、OKと声をかけて、緊張から解放してあげましょう。
「OK」と犬に声をかけて、思いっきリほめてあげて、「待て」のしつけが終わったことを伝えます。
例えば、3回練習をしたら、OKの声をかけて、犬を解放してあげます。
しつけのあと、解放してあげれば、メリハリがついて、犬も集中して、「待て」のしつけをしてくれます。
犬が待つことができなくて、飛びついてくるかもしれません。
飛びついてきたら、失敗なので、手最初から犬の待てのしつけをやり直しします。
犬に「待て」ができるしつけ環境を作ろう

犬が「待て」を上手にできるように、しつけをする環境を作っていきましょう。
静かな場所で集中
犬の「待て」のしつけをするときは、集中できる静かな環境で行っていきましょう。
おうちの中だったら、テレビやラジオなどは消します。
多頭飼いをしているなら、他の犬は別の部屋に移すなどして、しつけをする犬だけにします。
家族にも協力してもらい、静かにしてもらったり、洗い物や洗濯、掃除機の音も聞こえないようにしましょう。
しつけをするときは、犬が集中して、待てができるようにしましょう。
犬を冷静にさせる
犬の「待て」のしつけは、まずは犬を冷静で落ち着いた状態にしましょう。
犬が興奮した状態では、待てのしつけは、教え方がうまい人でもなかなかうまくいきません。
おもちゃで遊んだあと、とても興奮しています。
飛び上がるような状態だったら興奮をしずめて、落ち着かせてから行います。
ドッグランやおうちの中で走らせた後なども興奮しています。
しばらく時間をおいて、犬に待てのしつけをしていきましょう。
犬に「待て」の位置を変えてしつける

犬を横に座らせた状態で待てができるようになったら。いろいろな位置で待てるようにしつけていきましょう。
正面の犬の「待て」のしつけ方
犬の「待て」の教え方(正面)
- 犬をおすわりをさせる
- 犬の正面に立つ
- 犬に「待て」と低い声で短く声をかけながら、掌を犬の顔の前に向けます。
- 犬が静止したら、「OK」と待てを終了させる。
- 待ての成功です。犬をほめてあげましょう。
最初の犬の待ては、1秒でも十分なので、犬が待てができたことをほめてあげましょう。
犬に待てのしつけがなれてきたら、だんだんと時間を長くしていきましょう。
うちの愛犬も落ち着くがなく、1秒も待てができませんでしたが、何度もしつけをすることで、待てができるようになってきました。
横位置の犬の「待て」

今度は、犬を飼い主の横におすわりさせて、待てができるようにしていきましょう。
犬の待ての教え方(横)
- 犬の横に立つ
- 少し体をかがませて、犬の顔の前で、手のひらで静止して、待てと声をかける。
- OKと声をかけて、しつけ終了
- ほめる
犬を横に立たせてから、待てのしつけは、少し難しいかもしれませんが、頑張ってやっていきましょう。
ボクも犬の待ての教え方がわからず、悩んでいましたが、ビデオにとった自分の行動を見て、何がいけないのか、研究することで、待てのしつけができるようになりました。
正面と横の「待て」
今度は、犬を飼い主の横におすわりさせて、待てができるようにしつけていきましょう。
犬の待ての教え方(正面と横)
- 犬の正面に立ちます。
- 犬の顔の前で掌で静止して、待てと声をかける
- 犬の横に移動する。
- OKと声をかけて、しつけ終了
- ほめる
<<犬の「待て」の具体的なしつけの方法>>については、こちらでもご紹介しています。
犬から離れても「待て」ができるようにする
犬の待てのしつけがある程度習得したら。離れた場所からでも、待てができるようにしていきましょう。
離れた場所での待ては、犬がどこかにいかないようにロングリードを使います。
犬の「待て」のしつけ(離れる)
- 犬をロングリードにつなぎ、待てと声をかけます。
- 犬から離れます。
- 数秒経ったら、犬のところに戻ります。
- OKと声をかけて、犬をほめます。
犬の「待て」と「コイ」
犬の「待て」てをしつける時に、「コイ」も教えていきましょう。
犬の「待て」の教え方(待てとコイ)
- 犬に待てと声をかけて、またせる
- ロングリードを持ちながら、犬から離れる
- 「コイ」と声をかけて、ロングリードを引き寄せる。
- 犬がそばにきたら、OKと声をかけてほめる
犬がどこかに行きそうになった時、「待て」と言って犬を静止させて、「コイ」でこちらにくるようになったら、どんなに楽になります。
犬が「待て」と「コイ」がなかなかできないかもしれませんが、時間をかけて、教え方を工夫して何度も練習しましょう。
教え方に答えはありませんが、客観的に自分をみたり、犬のしつけのトレーナーさんからアドバイスをもらうといいですね。
犬の待てができるようになったら

待てを完璧にしておく
犬の「待て」のしつけは、一度習得したとしても、教え方が甘いと、失敗が増えてきます。
できれば毎日練習して、確実にできるようにしておきましょう。
犬の待ては、不意に手からリードを離れてしまった時、どこかに犬が行きそうになったとき、食べてはいけないもの食べそうになったとき、とても便利に使えるコマンドです。
犬がしつけで「待て」という命令で待つことができたら、犬や人間の安全確保にも、大変役に立つはずです。
おやつは使わない。指示だけにする
犬の待てがおやつでできるようになったら、おやつなしでできるよウにしていきましょう。
犬は、飼い主からほめられれば、とてもうれしいので、おやつがなくても、待てができるようになるはずです。
環境を変える
おうちの中などの静かなところで「待て」ができるようになったら、環境を変えてみましょう。
公園など雑音があると、待てができなくなってしまうかも。
犬を安心させて、ゆっくり「待て」をさせていきましょう。
子犬の「待て」の教え方のコツ。いつでも待てができるようにする
英語で待てを教える
犬のコマンドを英語でしつけをしている飼い主さんもいるでしょう。
英語で待てをしつけるなら、「stay」のコマンドで教えていきましょう。
あわせて読みたい
-

-
犬を「待て」を英語でしつけるには?待てができないときの教え方
2025/1/15
犬mの待ての英語は、「ステイ(Stay)」が一般的です。 「ウェイト(Wait)」でも構いません。 犬にしつけるときに重要なことは。 が大切です。 ストップでもかまわないのです。 モグワン公式サイト ...
犬が待てができない時は?

犬が待てができないなら、しつけのやり方を変えていきましょう。
時間を短くする
犬の待てのしつけができないなら、待ての時間を短くしてやりなおしましょう。
できるようのなったと思っても、何度も何度も短い時間でしつけをして確実にしていきましょう。
少し時間を長くして、また短い時間に戻す教え方をすると、犬も確実に待てができるようになるでしょう。
根を詰めてやっても犬が疲れるだけです。
ボクもなぜ待てができないの?と悩むこともありましたが、しつけは時間がかかるものです。
ゆっくりと時間をかけて、犬の待ての教え方をしたらできるようになりました。
距離を変えてみる
犬の「待て」の教え方は、距離感がとても大事です。
飼い主と犬との距離、おやつの位置などを見直してみましょう。
最初は、遠くから、そして徐々に近づけて待ての教え方をすると、難易度がだんだんと上がり、習得させるコツです。
おやつを変える
犬が「待て」ができないなら、も好きなおやつではないかもしれないので、おやつの種類を変えてみましょう。
しつけで使うごほうびのおやつは重要です。
臭い、大きさ、種類など、工夫していきましょう。
手を使う
犬が「待て」をしてくれないなら、手を使うのも有効な方法です。
待ての言葉と同時に、犬の顔の前に手のひらを出し、静止させます。
手を犬の前にすることで、犬が座っている状態から、立ちにくいこと、おやつが遮断されること、飼い主の強い意思が示されることなどの理由からです。
手を出さなくても、犬が待てができるようになったら、声だけで、待てができるようにしつけていきましょう。
他人にみてもらう
犬が「待て」ができないなら、ドッグトレーナーにみてもらうと、上達が早いです。
しつけは、犬に行動を変えさせるのではなく、飼い主が行動を変える必要があるからです。
おやつの位置、声の掛け方、姿勢など、何かしつけのヒントが見つかるかもしれませんよ。
>>犬が待てができない理由。いつでも待てができるようにするには
「待て」の前におすわりを習得
犬の「待て」は、おすわりの状態で待てをさせるようにしましょう。
立った状態だと、動いてしまう可能性が高くなるからです。
犬の腰を落とさせ、落ち着いた状態で「待て」ができるようにしつけていきましょう。
<<おすわりのしつけ>>については、こちらでお話ししています。。
犬の待てについてのよくある質問

いつから待てをしつければいいの?
犬の待てのしつけは、生後5ヶ月頃から、成犬になる1歳過ぎまでにすると、習得が早く、しっかりと身についていきます。
生後5ヶ月は、子犬の散歩デビューの時期と重なります。
安全に散歩ができるように、待てのしつけをしっかりとやっていきましょう。
待ての時に動いてしまうなら
犬が待てができず、動いてしまうのは、あるあるです。
犬が動いてしまうなら、待ての時間を短くしましょう。
おやつを手に持った瞬間に「待て」と声をかけて、すぐにおやつをあげるところから始めると、なんとなく待てとおやつが一致してきます。
そして段々と時間を長くしていきます。
失敗したら、おやつをあげず、何度でも待てのしつけをやり直していきましょう。
犬の「待て」のしつけをする理由

犬の待てをしつける理由についてお話しします。
犬に待てのしつけをする理由
- 他の人や犬から危険から守る
- 「待て」で感情を制御する
それでは1つずつお話ししていきます。
犬や他人から危険から守る
犬の「待て」のしつけをする理由は、犬や人を危険から守るためにとても大切なしつけです。
犬の「待て」のしつけはこんなとき役立つ
- 拾い食いをしそうになった時
- 家のドアが開いているのに気づかず、犬が外に出てしまった時
- 首輪がはずれた時
- 犬のリードが、手から離れてしまった時
- 犬が他の犬に攻撃的になろうとしている
- カフェでのんびり過ごしたい時
「待て」は、犬の特技として、ぜひしつけをしておきましょう。
「待て」で感情を制御する
犬は感情で動く動物なので、心をおさめるという意味では、待てのしつけは大切です。
犬の感情や欲求を制御し、飼い主さんのいうことを聞いてくれれば、飼い主さんもストレスなく犬との生活を楽しむことができます。
犬の待てのしつけができていうれば、勝手な行動もなくなり、従順な犬になって、育てるのが楽になるのです。
犬の待てのしつけは難しい?

犬の待てはとても大事なしつけですが、初心屋にとっては難しいかもしれません。
はじめて愛煙を迎えたとき、ご飯の前で「待て!」と号令をかけても、待てができずにとても悩んでいました。
言葉がわからない子犬にとっては、何を言われているのか、意味すら理解できません。
目の前のおいしそうなご飯があるのに、何を言ってるの?って感じです。
犬の待ては
待ったらいいことがある
と理解してからは、待てができるようになりました。
犬の待てのしつけのまとめ
今回は、犬の待てのしつけについて、お話ししました。
うちのミニチュアシュナウザー も、最初は待てがまったくできませんでしたが、時間をかけて、待てのしつけをしたら、できるようになりました。
犬の待てのしつけは、おうちの中だけではなく、外でもできるように、散歩の時などに、しつけの練習して起きましょう。
外は犬も車の音や雑踏など集中できないので、難易度がとても高いので、できたら一緒に喜びましょう。